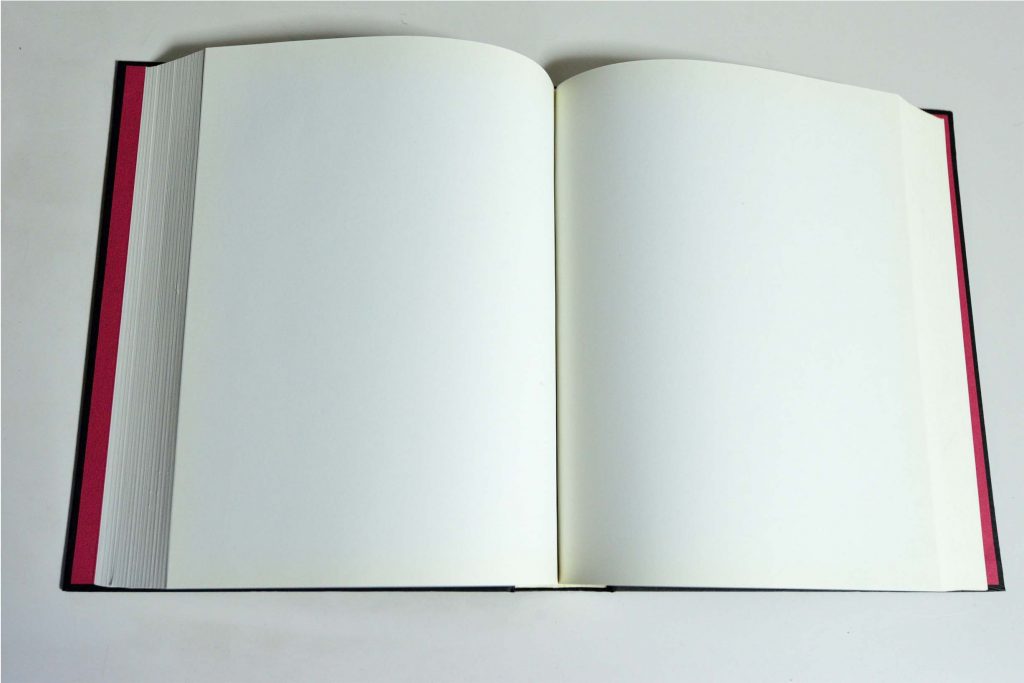自費出版の依頼者の多くは著者で編集者だから、書く事と読む事に全神経が集中するあまり、本の見た目へまで気がまわらないことはよくある。
手元にある本からくる、漠然とした「こんな感じ?」程度のイメージだろうか。
「この本の見た目って……、どんな感じになるのでしょう?」
こんな依頼者からの質問を「ひょいっ」とした感覚の意外性に感じてしまうのは、コチラ側もうっかり気がまわっていなかったせいもあるのだろう?
遠慮気味でボソッとした声が聞き取りにくく感じるのも、出版社とのやりとりでは無い声のトーンのせいだろうか?
「ああ、それはですね……」
まるで子供に本質的な質問をされ、困惑気味なラジオの大人の声を聞いているようになっている。
大人より子供の方が優れていることを感じさせられる、「偉大な瞬間」なのかもしれない。
しかしそこには、調性がない? 無調? 十二音技法?
感じた脳は、さっそく内側で語りはじめる。
「俺は知ってるよ。だけど良い子はそんな質問はしないもんさ」
「分かったつもり」を知っている大人たち。
「分かったつもり」を知らない子供たち。
「この本の見た目って……、どんな感じでしょう?」
大歓迎すべき声だ(でなければならない)。
正気に戻る。
「本の作り直しは製本後はできません。できてからのお楽しみではとても不安なのは理解できます」
「そんな方へは束見本をプレゼントいたしましょう」
束見本。その名の通り束(本の厚み)を知る目的で作られる見本として生まれた本。特別なことでなく、出版社からフツーに依頼されている本。
用紙の厚さは仕様書に表記がされてるから、束見本無しでも算出可能なので必ず作るものではない。
ただし最近は減ったが、箱(ブックケース)のある本は必ず作らなければならない。
箱が大き過ぎると緩くて本が落ちてしまう。小さ過ぎるとキツくて本の出し入れがやっかいだ。どちらにしても本を痛めてしまう。
この束見本。表紙も本文もすべて印刷されていないけれど、素顔の本とでも表現するべきか立派でカッコいい。
用が済んでほこりをかぶった姿の束見本を、出版社の本棚や机上で見かけることがよくある。その本を手に取り開いてみる。インクで汚されていない無垢な紙が目の前で広がると大変に美しいのだ。
この紙はどこかの国の、どこかの森林で一本の木としてどれほどの時を過ごしてきのだろう? その一本の木を想像することができるだろうか?
https://sankyobooks.jp/sankyo/index.html