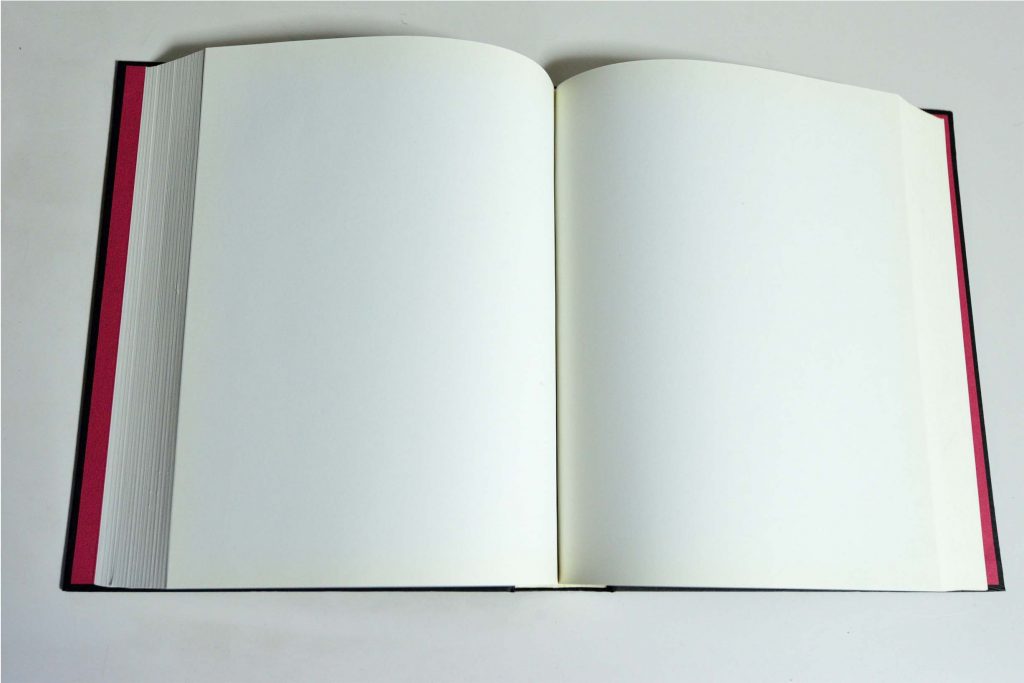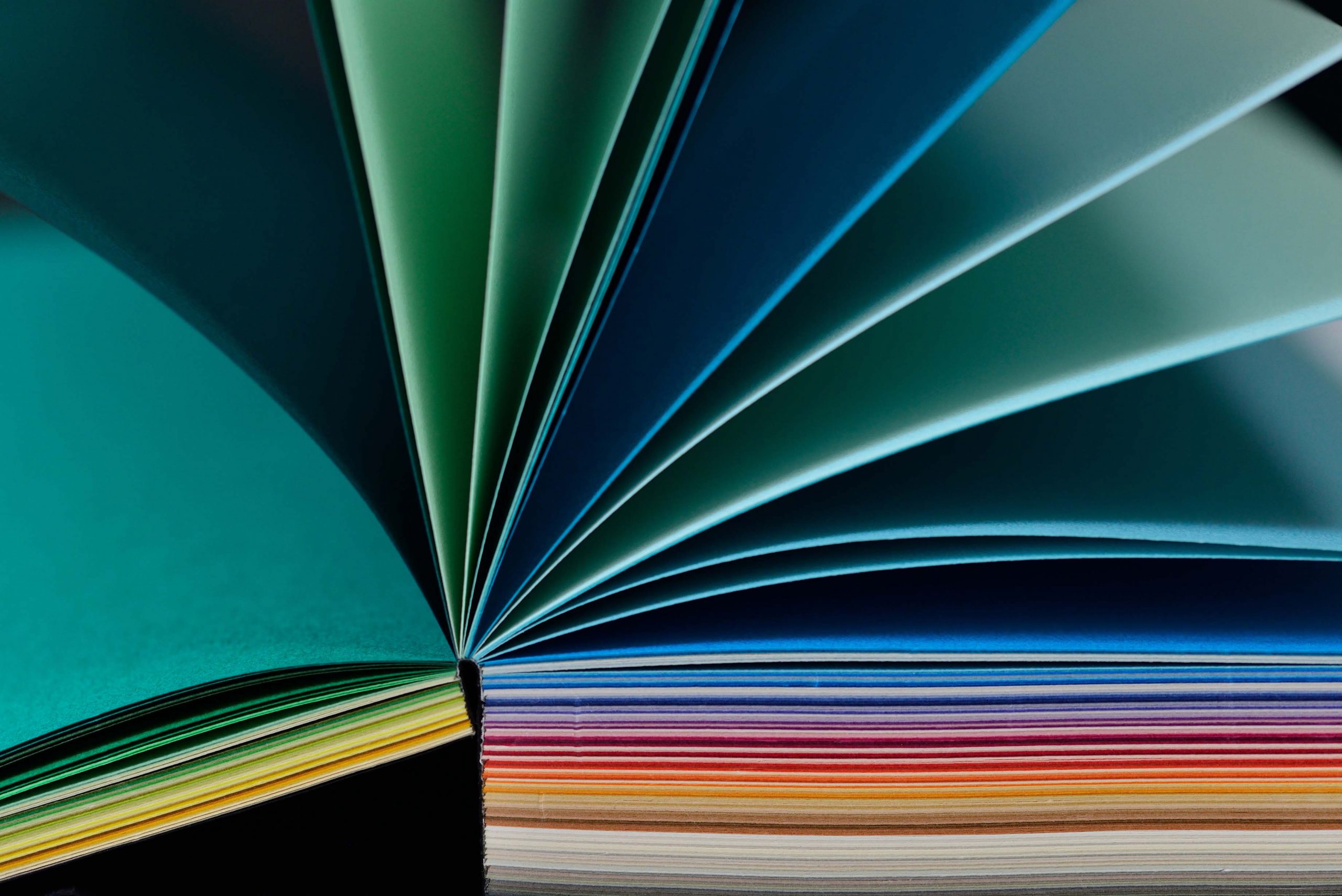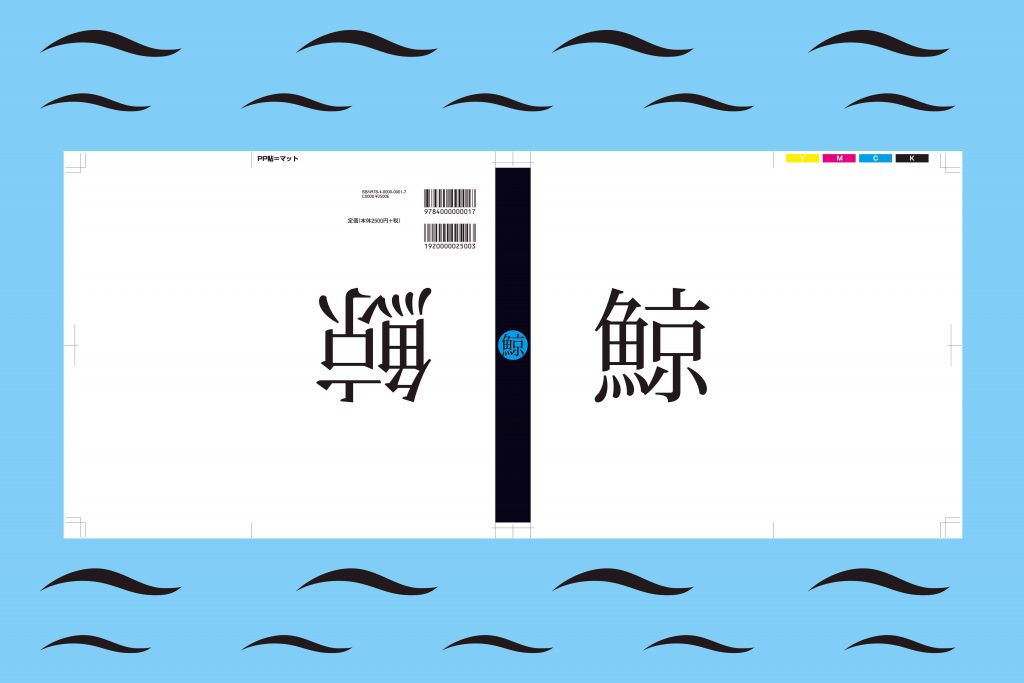ゴミの集積所で本たちを目にする時がある たいていは数冊で紐で結われている。
かつては書店の本棚で背文字を見せつけ、ヒトの視線を浴びていた本。
かつては一字一句、ヒトの視線に追われていた本。
今では路上に積まれ、収集車のお出迎えを待っている。
コロナウイルスの影響下、家庭ゴミが増える一方で、飲食店の休業が相次いだ繁華街ではゴミの減量が凄まじかったようだ。
「コロナでごみ激減、窮地の収集業者 感染リスクに不安も」(2020年6月2日配信・朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASN6236Q9N5QUTIL05C.html
食品ロス、ゴミの廃棄、焼却場などの問題が言われて久しい。誰もがゴミの減量は良いと思っているに違いない。が一方では、ゴミが減ると生活できなくなる人たちもいる。
見回せば、ほとんどのヒトは矛盾だらけに囲まれ生きていたということだろうか。
自然環境も、ヒトがわざわざ環境保護運動なんてしなくとも……。
「人が出ないと、現れた 街に動物・澄んだ水・青い空、…コロナ余波」(2020年4月19日配信・朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/DA3S14447645.html
原発事故の起きた福島・双葉町にかつてあった標語を思い出す。
「原子力明るい未来のエネルギー」
一部のヒトの間では、事故後の現在でも「未来のエネルギー」らしい。
新しい標語が待ち遠しい。それは「明るい」のか「暗い」のか。
「モノは使い捨てにしましょう。そして経済を回しましょう」
コロナウイルスはヒトが使い捨てだったことを明るみにした。
「モノもヒトも使い捨ての時代です。働けるだけ働いたらなるべく早く死んで経済を回しましょう」
記憶は人から消えゆき、人は記憶から消えゆく。
ゴミを収集するヒトとお迎えを受けた本、使い捨て同士が集積所で出会って焼却場へと走り去る。
https://sankyobooks.jp/sankyo/index.html